×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
諸法無我(sabbe dhammā anattā)は、「諸法非我」とも呼ばれることがある。
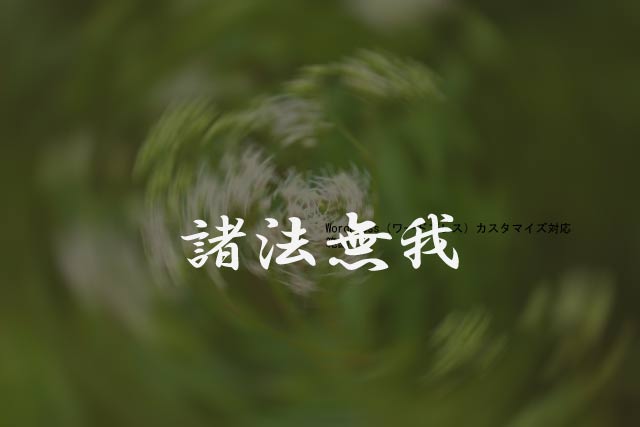
これは「我ならざるもの」というニュアンスをより一層的確に表現している。
諸法無我
諸法無我は、「あらゆる因縁によって起こっており、その中で固定的な我は無い」というような意味を持つが、我がないのであれば自我の認識自体が起こりえない。
よって我がないのではなく、我は我ならず、一切は因縁により生起された我ならざるものということが諸法無我である。
「諸法無我」は、あらゆる存在には固定的な自己が存在しないという教えである。自己というものは五蘊(色・受・想・行・識)の仮和合にすぎず、そこに本質的な「我」は見出せない。これもまた、理屈では納得できても、実際に自我が否定される経験は人に強い不安や恐れをもたらす。ウペッカーの実践は、この自我の脱構築に対しても非常に重要な役割を果たす。自分自身に対する執着すらも捨てる精神を養うことで、「無我」という仏教的リアリズムに心身ともに調和していくことが可能となる。
これは「我ならざるもの」というニュアンスをより一層的確に表現している。
諸法無我の「諸」は「一切の」とか「あらゆる全ての」であり、「法」は、「理」、「法則」、「揺らぐことのない真理」。無我は「我」というのは「固定的な実体」としての自分、自我を否定することを意味する。我を我だと思うこと、我を固定的な存在だとすることを否定している。これにはアートマンの否定の要素が強く反映されている。
諸法無我
あらゆる因縁によって起こっており、その中で固定的な「我」は無い
諸法無我は、「あらゆる因縁によって起こっており、その中で固定的な我は無い」というような意味を持つが、我がないのであれば自我の認識自体が起こりえない。
よって我がないのではなく、我は我ならず、一切は因縁により生起された我ならざるものということが諸法無我である。
「諸法無我」は、あらゆる存在には固定的な自己が存在しないという教えである。自己というものは五蘊(色・受・想・行・識)の仮和合にすぎず、そこに本質的な「我」は見出せない。これもまた、理屈では納得できても、実際に自我が否定される経験は人に強い不安や恐れをもたらす。ウペッカーの実践は、この自我の脱構築に対しても非常に重要な役割を果たす。自分自身に対する執着すらも捨てる精神を養うことで、「無我」という仏教的リアリズムに心身ともに調和していくことが可能となる。
PR

コメント